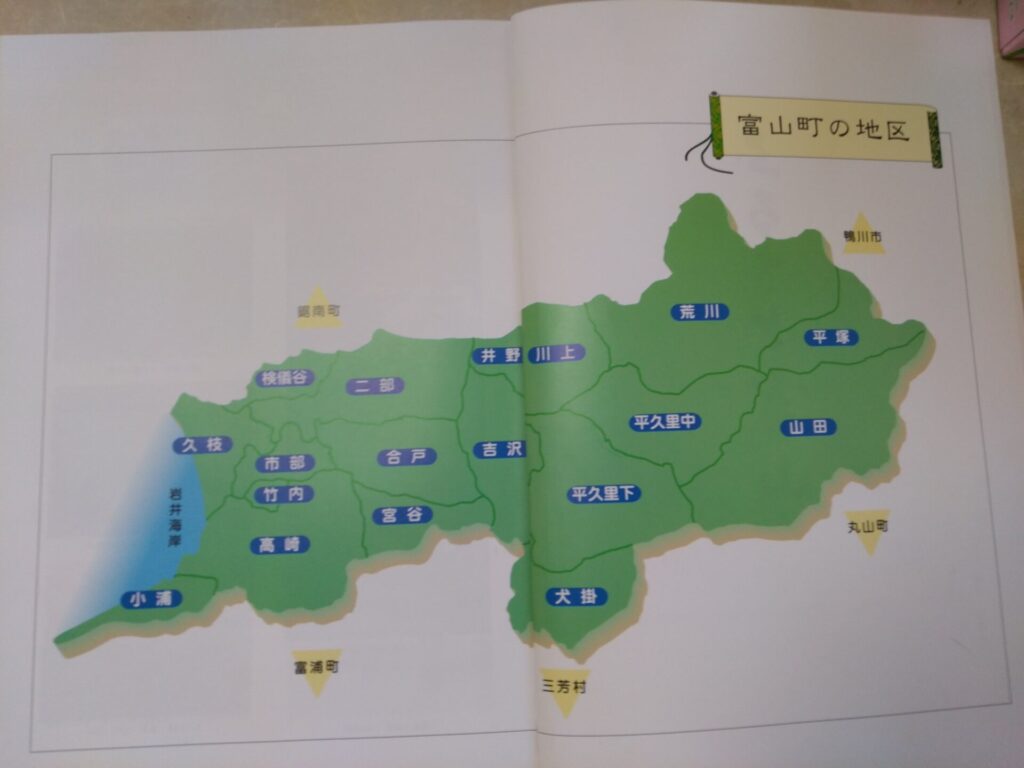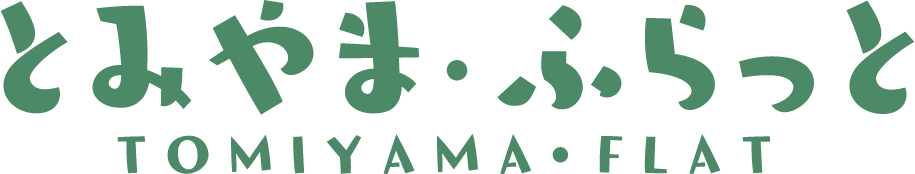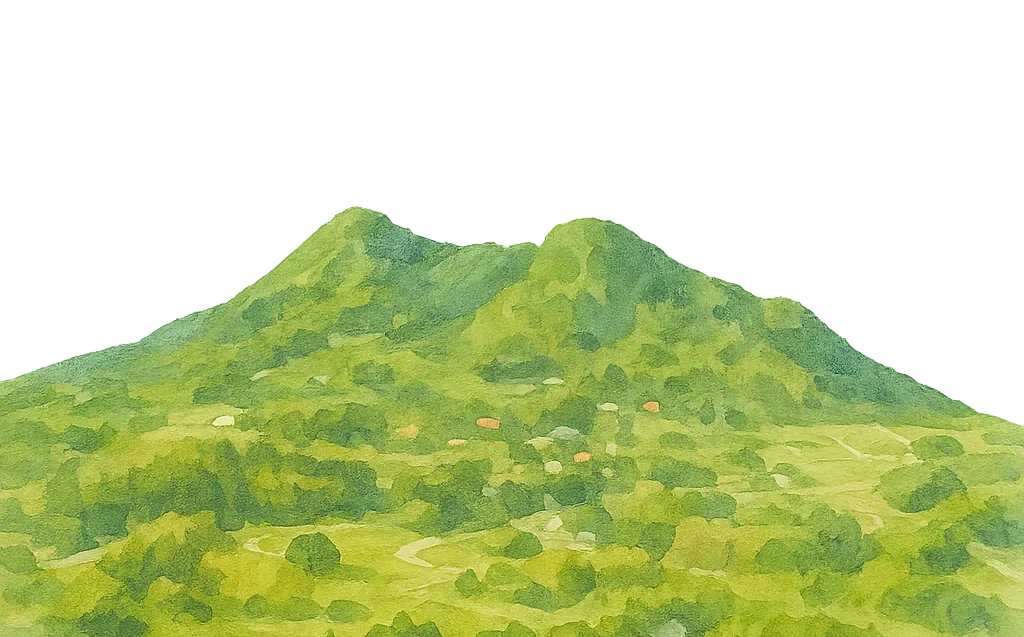富山地区の「高崎」は、小浦の東にある小高い丘である高崎から名付けられたもので、明治時代に高崎村として登場しました。小浦の漁港付近を高崎湾、岩井川の支流に高崎川という呼称もありますがどちらも古い名前ではないでしょう。崎は山が突き出たところを指し、高崎とは高く突き出た所という場所を表しています。
高崎の地区は江戸時代までは「不入斗」(いりやまず)とよばれていました。不入斗とは、藩への年貢を免除する地域という意味です。なぜそうなったかというと、不入斗村は鎌倉の鶴岡八幡宮の領地だったからです。これは地元の地頭の寄進によるものと考えられています。
不入斗は、土地に地頭が入れない「不入」と年貢米を量る「斗」の合成語でしょう。荘園が広がった鎌倉時代頃から登場する言葉で、富山町以外にも市原や富津にもあります。さらに広げると横須賀市にも不入斗という地名が残っています。
今ではあまり交流のない対岸の三浦半島と南房総には同じ地名がいくつもあります。これは鎌倉時代から幕府に関係する豪族が房総地域を領有していたからだと思われます。
以前紹介した「犬懸」は鎌倉の東北部にいた犬懸上杉氏と関係し、千倉にある「朝夷」(あさい)も鎌倉東部の朝夷名切通しを開いたといわれる朝比奈義秀と関係しているとも言われています。このほか、金谷や州崎という地名は神奈川にもあります。鯨漁の技術も相模の三浦の漁師の口添えがあったという記録があるそうです。このように、対岸の相模国との往来は今よりももっと密接だったのではないでしょうか。
(徳永忠雄)