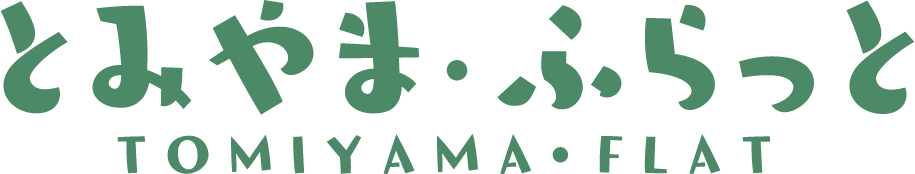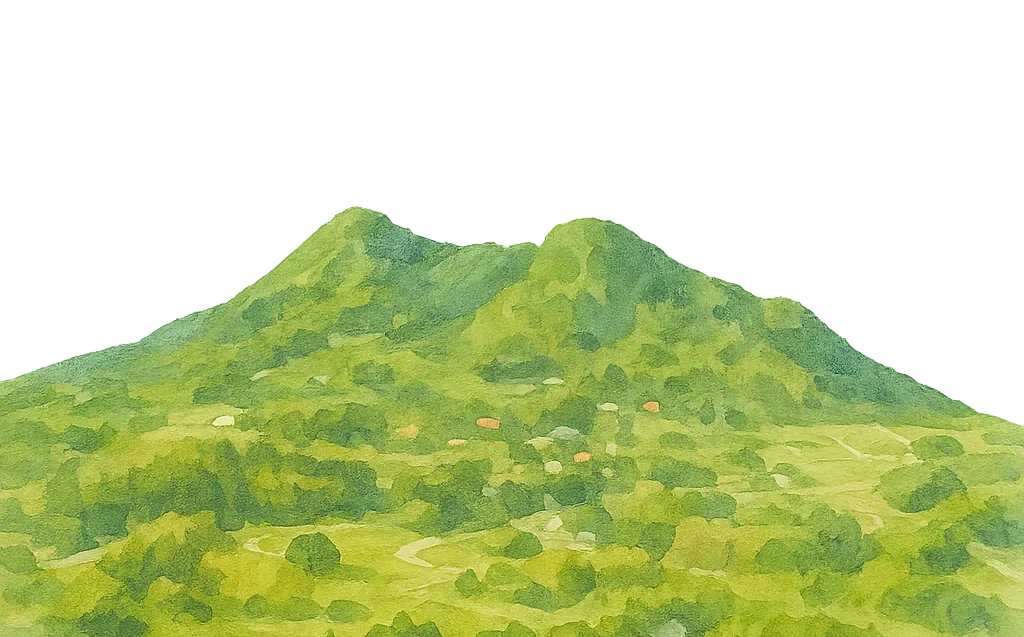江戸時代の中頃に作られた関東の豪農・豪商ランキングに二百名ほどの名が番付表のように紹介されており、その中に房州人が三人名を連ねています。その中の一人は、竹内治郎右衛門と書かれていました。もしやと思い「富山町史」を調べるとこの人物は竹内村の名主でした。職業欄には「田畑」と書いてあるのでまさに豪農なのでしょう。今から三百年前の記録です。
竹内という地名は、「峠のうち」がなまった「たうげのうち」から「たけのうち」になったという説もありますが、全国の多くの竹内は竹で屋敷の周りに囲み防御にした武士の屋敷を意味します。つまり竹に関わる屋敷を指す中世の地名あるいは苗字なのです。家の周りの竹垣はいざというときには弓矢の材料にすることさえできるからです。
房州に逃れてきた頼朝が訪れた竹内の網代家のソテツ伝説は有名で、近くに頼朝橋の名も残っています。さらにこの地区には戦の武具に関係する「具足原」という小字があり武士の存在を伺わせます。高崎の南には竹内地区の飛び地がありこれは要害山となって実際江戸時代の初期に見張りの城として使われたようです。
江戸時代の記録によれば、田は収益高により「じょうでん上田」「中田」「下田」に分けられましたが、竹内村は七割近くが上田で、畑も六割が上畑でした。ここは岩井川と大川に囲まれた水利に恵まれた地帯で「埋田」「改土田」という小字名があることから田の整備も盛んに行われたと考えられます。それほど広くない竹内村の人々は江戸時代になり農業に人一倍精を出したのでしょう。江戸にも知られた豪農・竹内治郎右衛門はその代表だったのです。
(徳永忠雄)