【南房総学】安房国札観音霊場を大正時代の絵葉書で巡る!
安房の国札三十四ヶ所観音霊場巡礼は、鎌倉時代、後掘河天皇在位の貞永元年(1232)に悪疫が流行し、飢饉にも襲われるなど、世情が惨憺たる有様だったことに心を痛めた時の高僧たちが相図って、安房国内に奉安する観世音菩薩にご詠歌を奉納し、厨子の帳を開いて巡り、拝んだことに始まるといわれています。
今回は、第十六番 石間寺・第十七番 清澄寺・第十八番 石見堂を巡りたいと思います。第一番から掲載順に観音霊場を訪れ、今昔を感じて見てはいかがでしょうか。
※説明文は、ちば南房総「安房国札観音霊場巡り」より抜粋
◆第十六番:石間寺(せきがんじ)/石のつま 峰よりおつる たきの水 むすぶこころは すずしかるらん
長狭街道から蛇行する加茂川を越え、小原寺を左に登った観音台に石間寺があります。「東陽山小原寺」「国札十六番観音」とある石碑の間を通ると正面に小原寺の本堂があり、左に抜けると小高い山に木が生い茂る樹林が。そのなかの苔むした急な石段を上りつめると三間四面の観音堂が姿を現します。かつては嶺岡山系に連なる山の頂上にあった石間寺。火災で伽藍を焼失し、その後観音台という場所に再興したといわれています。江戸時代の元文年間にも火災があり宝暦年間に再建されるも、明治33年の火災で焼失。同39年に同地にあった西福院と合併し、翌年に観音堂を再建して小原寺と改称し、現在に至る。
お堂の向拝には見事な龍の彫刻があり、作者は後藤義光の弟子の後藤義信とされています。
※現在の石間寺:https://bosotown.com/archives/47821

石間寺(せきがんじ)の大正時代の絵葉書
◆第十七番:千光山清澄寺(セイチョウジ)/ふきはらう 月きよすみの 松風に はまよりおきに たつはしらなみ
海抜383メートルの清澄山に建つ山岳寺である清澄寺。創建は宝亀2年(771)、不思議法師が虚空蔵菩薩を刻んでこの地に安置。のちに慈覚大師が12の僧坊と25の祠堂を建て、房州一の天台宗の大寺となりました。江戸時代の初めに真言宗の僧・頼勢法印が再興し、真言宗智山派の寺に。徳川家康の帰依を得て、10万石の格式がある本山格の寺になりました。
日蓮宗の開祖である日蓮聖人が入山したのは鎌倉時代の天福元年(1233)、12歳のとき。ここで修行に励んだ聖人は、さらに諸国で各宗の奥義を学んだ後、帰山。建長5年(1253)、32歳のときに清澄山旭が森で立教開宗の第一声をあげ、日蓮宗の布教活動を始めたとされています。一方で清澄寺は明治初期の廃仏毀釈の影響もあって衰退。明治24年に真言宗から日蓮宗に改宗し、日蓮宗大本山清澄寺となりました。
※現在の千光山清澄寺:https://bosotown.com/archives/898
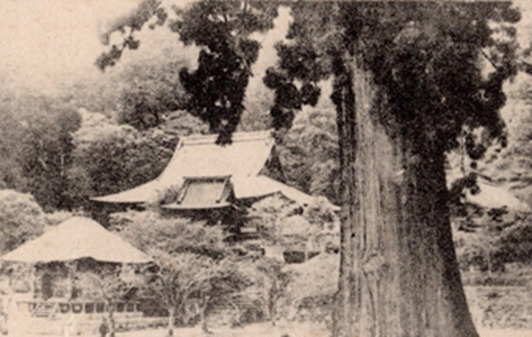
千光山清澄寺(セイチョウジ)の大正時代の絵葉書
◆第十八番:石見堂/石見堂 まいりて沖を ながむれば ふねにたからを つむぞうれしき
当初は西浜の海面に浮かぶ岩山にあったという石見堂。天保年間(1830~1844)に現在地へ移されたといいます。現在のお堂は明治15年に再建されたもの。現在は半㌔ほど離れた「金剛院」へご遷座しております。
ご本尊は真言宗の六観音のうちのひとつ、如意輪観世音菩薩。天上界を担当する観音菩薩です。如意輪観世音像は右手を頬にあてて考えるポーズをとっており、煩悩を破壊する仏法の象徴とされる如意宝珠を持っています。
ご詠歌に「船に宝を積むぞ嬉しき」とある通り、鴨川の漁港にほど近い場所にあり、お堂の周囲には古くから漁民の暮らしぶりが色濃く残っています。安房国札三十四ヵ所のご詠歌では、海や波を描いたものが多いですが、海に最も近い観音堂はこの石見堂かもしれません。
※現在の石見堂:https://bosotown.com/archives/15841

石見堂の大正時代の絵葉書

