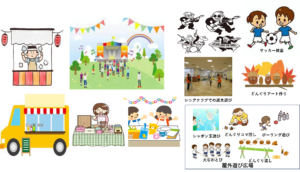【南房総学】安房国札観音霊場を大正時代の絵葉書で巡る!
安房の国札三十四ヶ所観音霊場巡礼は、鎌倉時代、後掘河天皇在位の貞永元年(1232)に悪疫が流行し、飢饉にも襲われるなど、世情が惨憺たる有様だったことに心を痛めた時の高僧たちが相図って、安房国内に奉安する観世音菩薩にご詠歌を奉納し、厨子の帳を開いて巡り、拝んだことに始まるといわれています。今回は、第十九番 普門寺、第二十番 石堂寺、第二十一番 智光寺を巡りたいと思います。第一番から掲載順に観音霊場を訪れ、今昔を感じて見てはいかがでしょうか。
※説明文は、ちば南房総「安房国札観音霊場巡り」より抜粋
◆第十九番:補陀洛山普門寺 /ふもん寺へ ひばらまつばら 分けゆけば めぐみも深き 岩やなりけり
天平19年(747)、行基菩薩が聖観音菩薩像を刻んで、一宇を建立したのが始まりといわれる普門寺。古くは山中にあって、岩戸観音と呼ばれていました。観音像は大正6年(1917)に威武山 正文寺の祖師堂へ移され、現在に至ります。
正文寺は12世紀に三浦半島から渡ってきた真田氏の頭領・真田源悟が創建した禅宗の寺。境内の洞窟の中には、真田氏の供養塔といわれる五輪塔が四基あります。天正2年(1574)に、勝浦城主・正木頼忠が父・時忠と正木家代々の菩提寺としました。正木家は日蓮宗の信仰に篤く日蓮聖人ゆかりの小湊誕生寺の末寺として日蓮宗に改宗しました。
祖師堂には頼忠が彫った日蓮聖人像と頼忠の娘で、のちに徳川家康の側室となった、お万の方の御駕籠を担いだ棒が展示されています。
※現在の正文寺(ショウブンジ)(補陀洛山 普門寺)のURL:https://bosotown.com/archives/836

補陀洛山普門寺(正文寺)の大正時代の絵葉書
◆第二十番:長安山東光院石堂寺 /ただたのめ 千手のちかい 両だすけ 二世あんらくを かけてたのめよ
和銅元年(708)、奈良の僧・恵命、恵照がインドのアショカ王の仏舎利を携えて当地に草庵を結んだことに始まり、神亀3年(726)に行基菩薩が聖武天皇の勅願により堂宇を建立。十一面観音菩薩像を刻んで本尊としたと伝えられています。
アショカ王の仏舎利宝塔を祀っており、日本三石塔寺のひとつと呼ばれています。
文明19年(1487)、野盗による火災でお堂や僧坊がことごとく焼失。当地の豪族である丸氏や里見氏の援助により、永正10年(1513)に現在地にお堂が再建されました。織田信長による比叡山焼き討ちの元亀2年(1571)には、退山した僧が天台師真影を護持して当寺に訪れ、寛政2年(1790)に比叡山に還座するまでの200年もの間、供養をされていました。その功によって総本山直末本山格となり、現在に至っています。
※現在の長安山東光院石堂寺のURL:https://bosotown.com/archives/494

長安山東光院石堂寺の大正時代の絵葉書
◆第二十一番:長楽山智光寺 /光明寺 のぼりのどけき はるの日に 山名のはなの ちるぞおしさよ
不動明王を本尊とする智光寺、千手観音を本尊とする光明寺、阿弥陀如来を本尊とする阿弥陀堂、この3寺が江戸時代中期に合併。現在に至るとされています。
光明寺はその昔、三郡山という山中にあった寺。三郡山とは、三つの郡の境、つまり長狭郡(鴨川市)、天羽郡(富津市)、周准郡(君津市)の三郡を示したもの。その後、江戸初期の元和年間に現在地に近い堀の内の観音山に再興され、元禄7年(1694)に智光寺境内へ移建されました。
千手観音を奉安する観音堂はもともと光明寺なので、ご詠歌にも「光明寺」と詠み込まれているのです。その後、智光寺は大きな火災に見舞われますが、お堂は宝暦13年(1763)に再建され、阿弥陀堂は安永4年(1775)に建築され現在に至ります。寺宝として市指定文化財の木造不動明王立像などがあります。
※現在の長楽山智光寺のURL:https://bosotown.com/archives/8802

長楽山智光寺の大正時代の絵葉書