【南房総学】安房国札観音霊場を大正時代の絵葉書で巡る!
今回で「安房国札三十四ヶ所観音霊場を大正時代の絵葉書で巡る」は終了となります。令和3年に予定されていました安房国札丑歳御開帳は、新型コロナ感染拡大のため中止となりましたが、次回は令和8年の牛歳御開帳が予定されていますので、巡ってみてはいかがでしょうか。
最終回は、第三十四番 滝本堂と、番外の 震災観音堂・観音寺・水月堂を巡ります。
第152号(3月発行)から掲載を始めた「南房総学」を楽しんで頂けましたでしょうか。
※説明文及び番外の写真は、ちば南房総「安房国札観音霊場巡り」より抜粋。
◆第三十四番 大山滝本堂:ごくらくの みのりはここに 大山の 千手のちかい なをもたのもし
かつて古畑にあった長徳寺という寺が、滝本堂の前身といわれています。長徳寺は鎌倉時代の貞永元年(1232)に慈悲上人が安房の観音霊場を定め、観音堂である滝本堂を三十四番納の札所に追加で選んだとのこと。
大永2年(1522)土豪の糟谷石見守家種が寺を再興し、寺号を大永普門寺長徳院と改め、千手観音菩薩立像を本尊に。天皇の勅願所として大いに栄えた時代もあったものの、明治維新後に廃仏毀釈の影響もあってか長徳寺は廃寺になったのです。明治34年に観音像を同じ大山にある大山寺へ移動。三十四番札所は引き継がれて、今に至っています。山の中腹にある大山寺は、諸武将の崇拝を集めた山頂にある高蔵神社の別当寺。神亀元年(724)良弁僧正の創建といわれています。
●現在の大山滝本堂の「ちば南防鼠 安房国f札観音霊場巡り」のURL:https://awa-junrei.jp/history/34takimotodou/
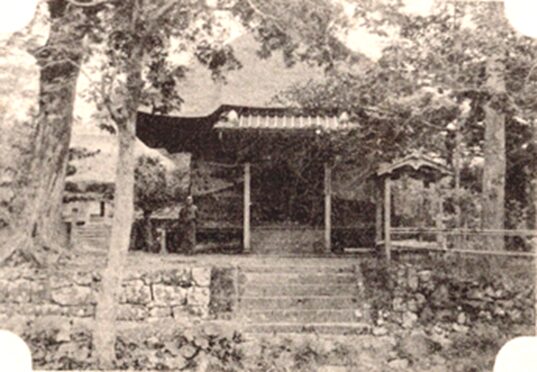
大山滝本堂の大正時代の絵葉書
◆番 外 震災観音堂:泡やとて たつまなきまに 消ゆる身は 同じ蓮の 花の臺に
一般に「震災観音堂」と呼ばれ「慈恩院」塔頭として多くの人々の帰依を集めています。御開山は、耕雲珍龍大和尚禅師。珍龍老師により「善導会館」が建てられ、改名され「観音堂」と銘々されました。お堂には後に北条から館山駅前に移転。その後、現在の海岸近く中村公園一隅に移転されました。二世巨海潜龍大和尚、現在住職、三世知音寛道。創建された趣旨は、大正12年9月1日に起き、未曾有の大被害を出した「関東大震災」による犠牲者の御霊を慰め、且つ「世界平和」の為、そして世の人々の「精神教化の一道場」たらしめが為、という発願のもと今日に至ります。
●現在の震災観音堂の「房総タウン.com」のURL:https://bosotown.com/archives/16592

◆番 外 福聚山観音寺:ありがたや まことの道に 手引きして ふかきえにしを むすぶみほとけ
保田駅の南東、日本武尊を祀る保田神社の前にある観音寺。八番日本寺と九番信福寺の中間に位置する番外寺です。縁起によれば、安房の太守・里見義実が文明3年(1471)に祈願所として建立し、本尊として新田義貞より譲り受けた聖観音立像を安置したのが始まりです。この観音像は弘法大師の作と伝えられています。その当時は真言宗の寺院でした。
その後、観音寺は、保田の曹洞宗昌竜寺の境外仏堂となりました。第二次大戦のときは本堂が茅葺だったために、空襲の被害を避ける目的で解体。現在のお堂は昭和30年に新築されたものです。
●現在の福聚山観音寺の「房総タウン.com」のURL:https://bosotown.com/archives/15225

◆番 外 大黒山大智庵水月堂:ありがたや 千手の糸を つずみ来て じひのみもとで 今ぞきるらん
漁師の街、勝山漁港をのぞむ大黒山。その中腹にある六番札所・長谷寺の隣に、番外観音堂の水月堂があります。水月堂が長谷寺に隣接された経緯は不明です。大智庵本堂裏の山裾にやすらぎ地蔵の祠があり、横の階段を上がると、こじんまりとした水月堂の境内と観音堂が。お堂は文和(ぶんな)4年(1355)の創建とされています。
元禄16年(1703)に起きた大津波では流失の憂き目に。当地でも多数の被害者が出ました。そこで供養に立ち上げったのは、勝山の捕鯨集団「醍醐組」の3代目・醍醐新兵衛明定(あきさだ)でした。
●現在の大黒山大智庵水月堂の「房総タウン.com」のURL:https://bosotown.com/archives/920


