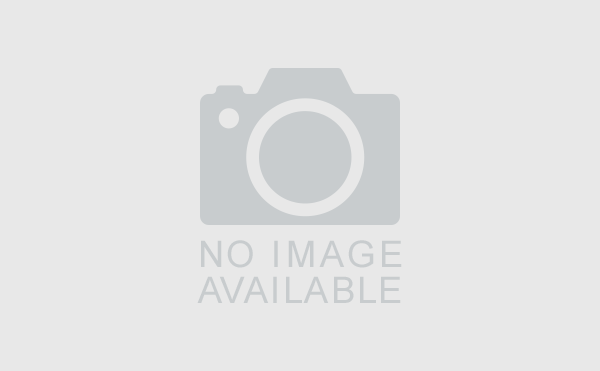1/16(火)ふらっとフットパス96を実施しました!
今回のフットパスは二部の水仙遊歩道から嶺岡林道を通り、下佐久間の熊野神社やカルピス発祥地等の以下のコースを巡りました。
●コース(約6.1Km+水仙遊歩道20分):
集合場所(富山ふれあいスポーツセンター駐車場)→富楽里前経由→水仙遊歩道(出口)→水仙遊歩道→元勝善寺跡→嶺岡林道経由→熊野神社→白銀・検儀谷経由→集合場所(11時45分頃解散)
今回は、ふらっとフットパスの年始めの会で、多くの方々にご参加いただき、新年の挨拶から始まり、能登の震災の被災の早い復興を各人で祈りました。
当日は小春日和の中、皆様、途中途中の説明を聞き、ダジャレ漢字クイズに答え、水仙街道の水仙と富士山を鑑賞し、往年のカルピスに思いを馳せながら元気にワイワイガヤガヤとウオーキングを楽しまれました。
最後のお土産(大根と菜花とスティックセニョール)を手に「次も楽しみにしていますよ!」と帰途に着かれました。
●今回の配布説明資料や説明内容などはウオーキング中の写真の後に記載されていますので、ご一読いただけると嬉しいです。😊

新年の挨拶から始まり、能登の震災の被災の早い復興を各人で祈りました!

水仙遊歩道の案内図

水仙遊歩道の水仙は満開でした!

二部のもと勝善寺後の高台でふらっと会員が岩井市部の佐久間秀雄童話集から野水仙(のずいせん)を朗読しました!

水仙遊歩道に行く前に岩井農協から富楽里にむかう一帯の田んぼは恩田原遺跡が広がっています。

二部から旧佐久間村の鋸南の方に下って来ました。

下佐久間の熊野神社でお参り&見学中!

熊野神社の鳥居の変還の説明版

途中富士山が綺麗に見えました!

カルピスの原液が下佐久間の白銀地区で作られたそうです。井戸が残っていました!
<フットパス96の説明資料>:
二部の水仙街道から嶺岡林道を通り、下佐久間の熊野神社やカルピス発祥地等を巡ります。
1.恩田原遺跡と銅印「王泉私印」:
恩田原遺跡は岩井海岸から東方へ約1km、標高10m前後の低位段丘上に位置し、JR内房線の東側にあります。岩井地区の圃場(ほじょう)整備事業に伴う、埋蔵文化財発掘調査が、平成7、8年に実施されました。
この時の発掘調査で、「王泉私印」と彫られた平安時代後期の銅印が出土しました。「王」の名がつくものとしては全国でも3例目で大変珍しいものです。匝瑳(そうさ)市の柳台遺跡から出土した「王酒私印」とともに、渡来系氏族の王氏に関わる私印と考えられます。当時の銅製私印は、主として地方官人層が所有していたと考えられるので、恩田原で出土した銅印所有者の「王」氏は、安房国の国や郡の行政に深く関わっていた可能性が推測されます。この銅印は、令和4年、県の指定文化財になりました。
<圃場整備>:
農地の区画整理、農道の整備、農業用排水路を一挙に整備するものです。 田を大きな区画にして用水をパイプライン化し、広い農道を作ることにより、大型機械の利用と容易な農業用水の管理が可能となり、農業生産性の向上を図ることができます。

銅印「王泉私印」(原寸)
2.房州水仙:
言い伝えでは、秀東寺(ひでとうじ)(鋸南町大帷子(おおかたびら))の和尚が、中国から持ち帰り、植えたのが房州水仙の始まりだと言われています。(年代不詳)
房州水仙は、江戸時代の中頃から、江戸の町屋や武家屋敷などで、もてはやされました。特に、正月を飾る切り花として珍重されました。
中村国香の紀行文「房総志科:宝暦11年(1761)」には、「平郡穂田芳浜辺の路傍に水仙多し、暖地なるゆえ花を著くること最も早し」とあります。
徳川幕府の老中:松平定信が、寛政4年(1792)11月に、異国船警備のため房総沿岸を巡視しました。その時の紀行文「狗(いぬ)日記」に、「ほたというあたりより、水仙いとおおく咲きたり」という記述があり、松平定信が簡単している様子がわかります。
3.旧下佐久間村:
鋸南町の元になる「保田村」、「勝山村」、「佐久間村」が明治22年(1889)に設置されました。勝山村は、「加知山村・下佐久間村・岩井袋村・竜島村」が合併し、成立した村です。加知山・下佐久間・竜島の各村は安房国平郡の佐久間郷に属し、岩井袋村は岩井郷に属していました。
江戸時代、勝山藩が成立すると各村は勝山藩領となりましたが、酒井忠胤(ただたね)が、2代藩主になると、忠胤は弟の忠成に3千石を分けて、旗本にしてやりました。この時、下佐久間村と竜島村は、旗本:酒井忠成の領地になりました。
4.熊野神社:
和歌山には、熊野本宮大社「主神:家都御子大神(けつみこのおおかみ)=スサノオノミコト」、熊野速玉大社「主神:熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)=イザナギノミコト」、熊野那智大社「主神:熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)=イザナミノミコト」の3社があり、熊野信仰の基になっています。また、それぞれの神は、仏の阿弥陀如来、薬師如来、千手観音と習合し、修験道の聖地にもなっています。
熊野神の使いである3本足の鳥「八咫烏(ヤタガラス)」も有名です。八咫烏は日本サッカー協会のシンボルマークにもなっています。日本サッカーの生みの親である中村覚之助が那智の出身であるのが理由のようです。平安時代の蹴鞠(けまり)の名人:藤原成通は、熊野詣によく出かけたそうです。
熊野神社は、全国に3000社以上あるそうですが、千葉県が最も多く、270社を数えるそうです。特に、安房を中心とする海岸地方に多く、黒潮がもたらした信仰と言えるそうです。
下佐久間地区の熊野神社は、伝聞では、「日本武尊東征のみぎり、熊野の神を祀りしに始まる」と言われます。記録としては、「慶長11年(1606)修造」「明治5年(1872)8月再建」が残るそうです。祭神として「熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)=イザナギノミコト」と「熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)=イザナミノミコト」が祀られています。熊野神社付近は古代人の遺跡で、昭和初年に石棒数本と黒曜石の鏃(やじり)等が出土したそうです。

熊野本宮大社

熊野速玉大社

熊野那智大社
5.カルピスの誕生:
大正8年(1919)7月、七夕の日にカルピスが発売されました。「初恋の味」というキャッチフレーズで、第一次世界大戦後の好景気の中で人々の心にぴったりマッチし、たちまち全国に広がっていきました。カルピスの名称は、三島海運社長による蒙古の酪農からの着想で、醍醐味の梵語:サルピスとカルシュームを合わせた造語です。宣伝で使用した下の絵は、第一次世界大戦後のドイツの芸術家の窮状を救うため三島社長が懸賞金付きで募集した作品の中から選ばれたものです。
このカルピスの原版が、「下佐久間の白銀で作られていた」と鋸南町史に書かれています。
伊豆大島出身の田留文吉が、大正7年、保田に小工場を設置し、保田近在の牛乳を買い入れて、カルピス原料の製造に着手したそうです。その後、大正10年2月に下佐久間の白銀にあった日本練乳勝山工場を借り受け、東京菓子勝山工場(元森永製菓の勝山生乳工場)から原料乳を仕入れ、カルピスの原液を樽詰めして、カルピス東京工場へ出荷していたそうです。太平洋戦争中の中断を経て、昭和24年8月に工場閉鎖となったそうです。

カルピスの初期のポスター

田留 文吉
<参考>:
・富山町作成の「恩田原遺跡」調査報告
・鋸南町史、富山町史、他