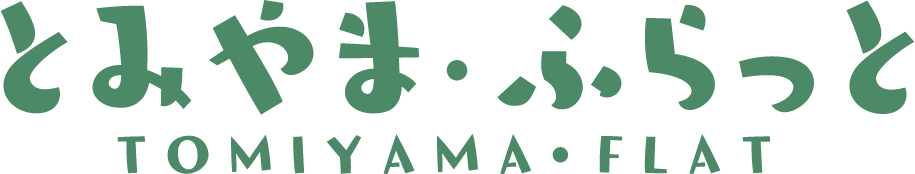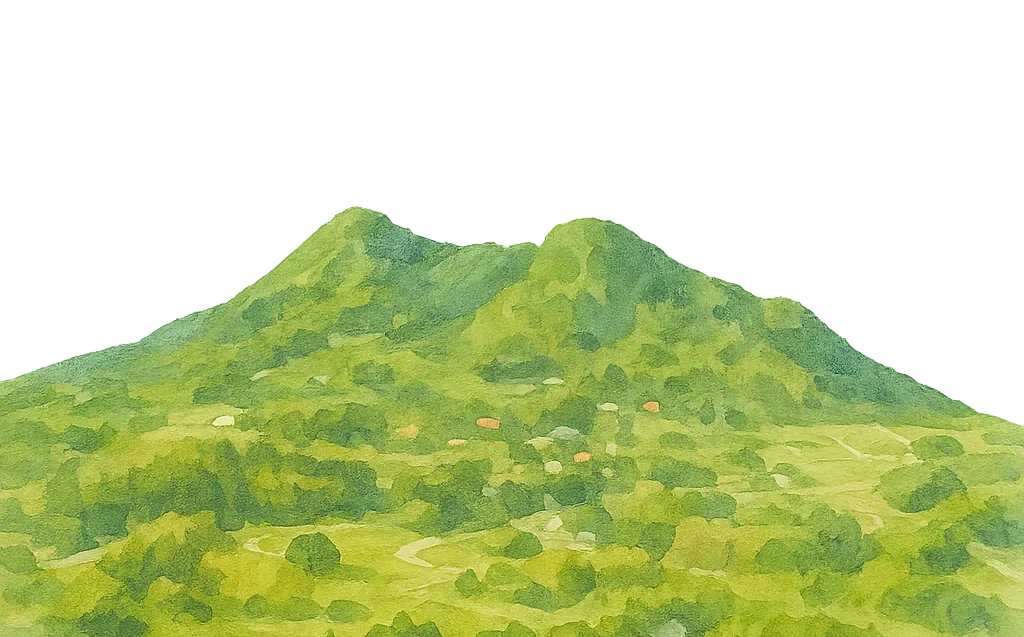今回のフットパスは、夏目漱石が海水浴をしたことで、「房州海水浴発祥の地」となった保田海岸や西条八十の童謡「かなりや」に関係するといわれる三瓶幸さんの旅館「加都満(かずま)」跡などを以下のコースで訪れました。
●コース (約7.5km):
集合場所(鋸南町中央公民館前の「道の駅きょなん」)出発(9時)→別荘:滴水居→海岸経由→師宣生誕地→旅館「加都満」跡→観音寺→存林寺→汐止橋→保田温泉踏切経由→鶴ヶ崎神社→元名海岸→「房州海水浴発祥の地」碑→海岸経由→集合場所(11時45分頃解散)
今回も多くの方々にご参加いただき有難うございます。_(_^_)_
晴れて暑いが風が若干強かった中、海岸沿いも歩き、途中途中、川名修さんの史跡説明やクイズ、ケーキ等のおやつを楽しみながら、皆様は元気にワイワイガヤガヤとウオーキングを楽しまれました。
最後のお土産(カーネーションとスターチス)とプレゼントの房州枇杷を手に「次も楽しみにしていますよ!」と帰途に着かれました。
●今回の配布説明資料はウオーキング中の写真の後に記載されていますので、ご一読いただけると嬉しいです。😊

いつもの出発前の体操中!

滴水居へ向かう途中!

滴水居が在った場所
氏の説明中!-1024x768.jpg)
「滴水居」と小泉丹(まこと)氏の説明中!

小泉丹が習字で小泉賞を贈っていた「吉浜小学校跡の案内板」
-1024x768.jpg)
「菱川師宣」誕生の地へ向かう途中(海岸の風はやはり強いね!)

「菱川師宣誕生地」の案内板

「菱川師宣誕生地」の説明中!
がいた元旅館「加都満(かずま)」跡での説明中!-1024x768.jpg)
西条八十に可愛がられていた三瓶幸(こう)がいた元旅館「加都満(かずま)」跡での説明中!

「観音寺」へ向かう途中!

「観音寺」の看板

観音寺」の説明中!
!が-1024x768.jpg)
「亀福山存林寺」内で休憩中!(ご参加者から配られたパウンドケーキが美味しい!)

「亀福山存林寺」の看板

「存林寺須弥檀彫刻」の案内板

亀福山存林寺

「汐止橋」の案内板

「汐止橋」の説明中!

休憩&漢字クイズ中!

鶴が崎神社の説明中!

「房州海水浴発祥地」石碑へ向かい元名海岸を行く!

「房州海水浴発祥地」の石碑

「房州海水浴発祥地」の石碑の説明中!

「房州海水浴発祥地」の石碑の裏面

「房州海水浴発祥地」の石碑の裏面の記載内容の説明中!
とプレゼントの房州枇杷-768x1024.jpg)
お土産の花束(カーネーションとスターチス)とプレゼントの房州枇杷

お土産の花束とプレゼントの房州枇杷をお渡し中!
<配布説明資料>
夏目漱石や西条八十など有名人ゆかりの保田を歩きます。
「ふらっとフットパス111(令和7年6月)」
1.「楽土」房州:
明治維新後の近代化は、都市の発達や交通網の整備とともに、人々の生活に保養や観光をもたらしました。東京に近く、海に囲まれた温暖な気候の房総半島は避暑や海水浴に訪れる人々でにぎわい、観光案内で「楽土」とも称されました。
2.「滴水居」:
慶応義塾大学の教授で、生物学者(動物学・寄生虫学)の小泉丹(まこと:1882~1952)が、昭和初期に避暑や海洋生物の研究のため建てた別荘が、「滴水居」です。房州石の石組みで作られたベランダとポーチ(車寄せ)を持つ、コテージ(別荘)風の建物です。「保田文庫」を出している前田宣明さんによると、小泉丹は地域の人ともよく交流をしていて、地元の小学校(吉浜尋常小?)の習字の優秀者には、「小泉賞」も贈っていたそうです。
3.西条八十と保田:
軍歌の中でも有名な「同期の桜」、戦後復興期のヒット曲「青い山脈」、村田英雄のヒット曲「王将」などの作詞で知られる西条八十は、保田と縁がありました。
西条八十は明治25年(1892)、東京で生まれました。旧制早稲田中学校に入り、その頃から、房州の海が好きでよく遊びに来ていたようです。
西条八十の晩年の手紙の中に、「私の海の作品は、房州海岸が基調になっています。」「元名という海岸で一人で泳ぎ、その時知り合った一少女が、太平洋戦争前まで、よくビワを送って来てくれたものでした。」などとあるそうです。
この「一少女」とは、保田の駅前通りの元旅館「加都満(かずま)」の三瓶幸(こう)さんのことだそうです。出会った当時は、出口半三家の娘で、八十に可愛がられ、よく一緒に遊んだそうです。
20歳になった八十は、横須賀の小料理屋で苦労して働いていた幸さんに再会することができましたが、すぐに別れなければなりませんでした。西条八十が、後に書いたエッセイの中に、「別れてから、便りはなかったが、毎年初夏になると、安房名物の南無谷びわを送ってくれた。」「ぼくは汽車の窓から保田の町をながめ、もう60を越したであろうお幸ちゃんが、この町に帰り住んでいるかどうか考えていた。」とあるそうです。
大正7年(1918)に発表され、八十が詩人として世に出るきっかけになった作品が童謡「かなりや」です。その歌詞に出て来る「唄を忘れたかなりや」とは、20歳になった八十がお幸さんと再会した時、お幸ちゃんが辛い境遇に置かれていたということへの「追憶」かもしれません。
4.観音寺:
聖観世音菩薩を御本尊とする真言宗のお寺で、正式には「福聚山観音寺」と言い、安房国札観音霊場の「番外」になっています。文明3年(1471)に里見義実が開山したと言われ、御本尊は新田義貞から譲り受けたと言われます。
天文4年(1535)に里見義堯(さとみよしたか)が、北条氏の要請を受け、川越を攻撃するために軍を送りますが、その時には本営が置かれました。
関東大震災の時は、保田・勝山で約180人の負傷者が出て、観音寺には救護所ができ、被災者の救護にあたったそうです。現在、震災記念碑が建っています。
現在の堂宇は昭和30年に建てられたものです。
5.汐止橋:
元名川にかかる石積みアーチ構造の石橋です。明治時代になると西洋の技術が導入され、安房地方でも石積みアーチ橋の技術が普及しました。この橋の特徴は、アーチングに向かって石が斜めに積まれているところです。技術の高さや形の美しさから日本土木学会から近代土木遺産に設定されています。使われている石は、鋸山から切り出された「房州石」です。
6.鶴が崎神社:
終戦までは保田郷の「郷社」という社格の神社でしたので、保田全体を代表する鎮守でした。祭神は、応神天皇(誉田別神)で、慶長の末から元和の初め(慶長元年=1596、元和元年=1615)の頃、創建されたそうです。
7.夏目漱石と正岡子規:
夏目漱石と正岡子規は、慶応3年(1867)生まれの同い年です。二人は明治17年(1884)、東京大学予備門(後、第一高等中学校と改称)に入学しました。親友としての付き合いは、明治22年の正月にはじまりました。
23歳で第一高等中学校本科2年生だった漱石は、明治22年8月7日、4人の友人とともに、房総への旅行に旅立ち、旅行後に書いた紀行文「木屑録(ぼくせつろく)」を子規に届けました。
<漱石の日程>
・8月7日、東京の霊岸島から汽船で保田へ(当時、4, 5時間で)
・船上、大嵐で麦わら帽子を飛ばされる
・保田海岸で海水浴、鋸山登山
・明鐘岬(富津市と鋸南町の境にある岬で森沢明夫の小説『虹の岬の喫茶店』のモデルとなった「岬カフェ」がある場所としても知られています)の連続する5つのトンネルを歩く
・勝山海岸の巨岩「巨人の拳」を見に行く
・10日間の保田滞在(推定)後、北条・館山へ
・小湊の「鯛の浦」「誕生寺」に寄る
・東金経由で銚子へ、その後、利根川や江戸川を利用
・8月30日に帰宅(現在の新宿区喜久井町)
・9月9日、「木屑録」脱稿。正岡子規に届ける。
8.夏目漱石の小説「こころ」:
「Kはあまり旅へ出ない男でした。私にも房州は始めてでした。~略~たしか保田とか云いました。~略~私はとうとう彼を説き伏せて、其所から富浦へ行きました。富浦から又那古へ移りました。総てこの沿岸はその時分から重に学生の集まる所でしたから、何処でも我々には丁度手頃の海水浴場だったのです。Kと私は能く海岸の岩の上に座って、遠い海の色や、近い水の底を眺めました。岩の上から見下ろす水は、又特別に綺麗なものでした。赤い色だの藍の色だの、普通市場に上がらないような色をした小魚が、透き通る波の中をあちらこちらと泳いでいるのが鮮やかに指されました。」
9.石碑:房州海水浴発祥地
保田海岸に「房州海水浴発祥地」の石碑があります。碑文には夏目漱石がこの海で泳いだ主旨が刻まれ、それが房州海水浴の始まりであると記されています。
石碑の「房州海水浴発祥地」の文字は、哲学者で法政大学総長などを務めた谷川徹三さんです。碑文には、昭和丙寅七月」とあり、丙寅(ひのえとら)が、昭和50年(1972)であることから、この年に建立されたことがわかります。
谷川徹三さんが揮毫(きごう:文字や絵をかくこと)してくれたことについては、現在の鋸南町の職員に尋ねてもわからないそうです。房日新聞の忍足利彦さんは、「房州ヘリテージ」の連載記事の中で、谷川徹三さんが夏目漱石の門下生の四天王の一人だったことを調べ、「夏目漱石」の縁で誰かが依頼したのではと推測しています。
10.大正時代の絵葉書:
下の絵葉書は、平成21年6月23日付け「房州新聞」に掲載されたものです。大正時代のもので、夏目漱石が房州を訪れた明治22年と少し年代の開きはありますが、海岸の風景はほぼ同じと考えられます。「東京と保田を結ぶ汽船」は、東京の霊岸島から保田へ来た「第13通快丸」で、元名平島のあたりです。

東京と保田を結ぶ汽船

元名海岸での海水浴
<参考>
きょなん資料館、関 宏夫箸「漱石の夏休み帳」、その他