6/8「ふらっとフットパス91」を実施しました!
今回は、徳川家康が食べる鮮魚を鷹狩りの場所の東金へ送っていた歴史がある岡本海岸を歩き、鯛漁発祥の石小浦を訪ねました。併せて日本地図を作製した伊能忠敬の足跡も含めてた、以下のコースを巡りました。
●コース(約 8.7Km、ほぼ平坦な道):
集合場所(とみうら元気倶楽部(富浦町原岡88-2)正面入り口横)→岡本川沿い・西方寺・岡本海岸経由→小学校下→逢島豊岡海岸経由→国道坂下トンネル北側→海岸への旧道・南無谷海岸経由→南無谷海岸北端→石小浦→南無谷海岸北端→南無谷海岸・国道への旧道経由→国道坂下トンネル北側→豊岡バス停から旧道・商工会前・駅裏経由→集合場所(12時頃解散)
当日は晴天の暑さにも負けず、皆様、途中途中の説明を聞き、素敵な海岸沿いの景観を楽しまれ、熱中症にならないように休憩を多く取り、元気にワイワイガヤガヤとウオーキングを楽しまれました。
最後のお土産(トウモロコシと枇杷(民宿すなだ様からのご厚意のプレゼント))を手に「次も楽しみにしていますよ!」と帰途に着かれました。
●今回の配布説明資料や説明内容などはウオーキング中の写真の後に記載されていますので、ご一読いただけると嬉しいです。😊
-1024x768.jpg)
いつもの出発前の体操中!(琵琶倶楽部横の広場)
)-1024x768.jpg)
琵琶倶楽部の左側にある冨浦の村章(栄光の軌跡:琵琶と「と」の三つ巴を形どっている)

富浦の村章の説明中!
-768x1024.jpg)
いざ、出発だ!(岡本川沿いの道)

岡本の西芳寺訪問

伊能忠敬が泊まった西芳寺の説明中!
-1024x768.jpg)
西方寺の名主地蔵の説明版(南房総昔話)
-768x1024.jpg)
岡本桟橋(木製桟橋)

岡本桟橋で景観を観て、休憩中!

岡本桟橋の夕日写真の看板
-1024x768.jpg)
岡本桟橋の落書き板(「フットパス91」と記載!)
-1024x768.jpg)
豊岡海岸を目指して海沿いを歩く(天気が良くて良かった!)
-1024x768.jpg)
日陰で休憩中(暑いわね!)
-768x1024.jpg)
豊岡海岸へ向かう途中2(向こうに「日蓮ゆかりの袈裟掛けの松」の碑がある)
-1024x768.jpg)
昔の醤油工場が有った場所(アメリカのスクールバスがある施設)

「小三郎坂」の説明中!

真ん中の低い場所が「小三郎坂」
-1024x768.jpg)
石小浦へ向かう途中で休憩中!(南無谷海岸)

休憩中のそばの素敵な家

石小浦の全景!

石小浦の「弥三兵衛生簀」

石小浦の「弥三兵衛生簀」の説明を聞き、見学中!
-768x1024.jpg)
石小浦からの帰り道(旧南無谷トンネルが涼しいね!)
-1024x768.jpg)
集合場所へ戻る途中!(南無谷海岸、向こうに雀島、舟虫島が見える)
-768x1024.jpg)
集合場所へ向かう途中!(富浦駅近く、集合場所まであと少し、ちょっと疲れたね!)

お土産はとうもろこしだ!

「枇杷」もご厚意のプレゼントだ!
<今回の配布説明資料や説明内容など>
Ⅰ.説明内容等:
1.小三郎坂:
岡本(豊岡)から南無谷へ抜ける険しい崖道がある。あえぎながら登る日蓮を近在の漁師小三郎が背負って登ったという。この坂道を「小三郎坂」と呼ぶようになった。
※館山博物館の「日蓮聖人とその伝説(内房編)」から抜粋

小三郎坂の地図

小三郎坂
2.法華崎遊歩道の雀島と舟虫島:
富浦町豊岡地区から南無谷海岸にかけて法華崎遊歩道の途中にある。
※現在、以前の台風15号後の落石の為、遊歩道は立入り禁止となっています。
※今からおよそ300年前の1903年に発生した「元禄地震」でできた元禄段丘が残る南無谷崎

左側が雀島、右側(陸側)が舟虫島

左側が雀島、右側(陸側)が舟虫島
3.多寿花(だしのはな):
江戸(えど)から明治(めいじ)・大正(たいしょう)の時代(じだい)にかけて、富浦(とみうら)の代表的(だいひょうてき)な物産(ぶっさん)に、「多寿花(だしのはな)」と呼ぶ(よぶ)醤油(しょうゆ)がありました。その醤油(しょうゆ)の醸造販売(じょうぞうはんばい)を行った(おこなった)人(ひと)は、汐入(しおいり)に住んで(すんで)いた川名宗兵衛(かわなそうべえ)で、嘉永年間(かえいねんかん)(一八四八~一八五三)に、汐入川上流(しおいりがわじょうりゅう)の地(ち)から、原料(げんりょう)や製品(せいひん)の搬入積送(はんにゅうせきそう)に便利(べんり)な汐入川(しおいりがわ)の川口(かわぐち)に店舗(てんぽ)を移し(うつし)ますと、大規模(だいきぼ)に醸造(じょうぞう)を開始(かいし)したのです。
大正十二年(たいしょうじゅうにねん)(一九二三)の関東大震災(かんとうだいしんさい)によって工場(こうじょう)が破壊(はかい)され、更(さら)に経済不況(けいざいふきょう)の余波(よは)を受け(うけ)、企業(きぎょう)すべてを閉鎖(へいさ)する事(こと)になったからです。
栄枯盛衰(えいこせいすい)は世(よ)の常(つね)。汐入川(しおいりがわ)の川口(かわぐち)に、大規模(だいきぼ)な石垣(いしがき)を積んだ(つんだ)屋敷跡(やしきあと)がありますが、その場所(ばしょ)が「多寿花(だしのはな)」の跡(あと)です。
その前には「ROMI’s OCEAN/ロミズオーシ」があり、アメリカンバス内や屋外でハンバーグやタコライスが食べれます。
日本財団図書館の「冨浦の昔ばなし 第二集」の資料より
●旧南無谷トンネルは、明治31年頃に完成していそうです。全長191m、幅3.9m、高さ3.4mあります。旧国道で、今では電気がついていますが、昔は、電気がなく真っ暗だったそうです。
4.出発前の謎かけ:
(1)典型的な鬼の絵で牛の角と寅模様のパンツを履いているのは何故?
→ 十二支の丑寅の間の方向が鬼門であるので、牛の角と寅模様のパンツを履いている。
(2)地図の縦の経線は別名、何て言うの?
→ 子午線と言い、時計の十二支の12時の子(北)と6時の午(南)を結ぶ線なので、そう呼ぶ。
「子午線」という語は、子の方角(北)から午の方角(南)に伸びる線(大圏)を指している。これは方角を十二支に当てはめるやり方からきている。夜の0時を「正子」、昼の12時を「正午」と言うのも、同じ起源である。
子午線は「北極と南極を結ぶ赤道と直角に交わる南北の線のこと。」
Ⅱ.配布資料:
家康に鮮魚を送っていた歴史がある富浦の海辺を歩き、鯛漁発祥の石小浦を訪ねます。
1.伊能忠敬(いのう ただたか)が岩井や冨浦にもやって来た:
実地測量に基づいて、はじめて日本地図を作った伊能忠敬の名は不滅の輝きを放っています。幕末、イギリス艦隊が日本の沿岸を測量した時、伊能の地図を見て極めて正確なのに驚いたそうです。
忠敬は、延享2年(1745)、上総国小関村(現:九十九里町小関)で生まれ、17歳の時、佐原村(現:香取市佐原)で酒造業を営んでいた伊能家に婿入りしました。そして、商人としての才覚を発揮し、伊能家の年間収入を約3.6倍まで伸ばしたそうです。
49歳で隠居し、50歳で江戸に出て、19歳年下の気鋭の天文学者、高橋至時(よしとき)に弟子入りしました。そして、軽度1分の距離を測定したりする中で、地球の大きさを計算しようと忠敬は考えるようになりました。
ロシアの船が姿を見せていた蝦夷地(北海道)の地図作成を名目に、幕府から許可を得て、寛政12年(1800)、55歳の忠敬は蝦夷地へ行きました。この時の測量をもとに作成された地図は、精巧で幕府からの評判も上々で、その後も、測量は9回、17年にわたって行われました。
房総半島の測量を行ったのは、享和元年(1801)です。忠敬の一行は、旧暦6月19日の午前8時頃、江戸・深川を出発しました。
測量日記には、「6月29日、忠敬は従者8名と共に、本馬一疋(ほんまいっぴき)、長持ち一棹、駕籠一艇の荷物を持って、勝山村の平井家を午前7時頃出発して、岩井袋村(104軒)→久枝村(135軒)→不入斗村(いりやまずむら)(現:高崎194軒)→小浦村(98軒)→南無谷村(174軒、富士山の方位を測る)→坂之下村(現:豊岡79軒)→岡本村(222軒)と歩き、午後4時過ぎに到着。宿は西芳寺」と書かれています。
また、夜には天体観測を行っていますが、測量日記には「寺の木々が覆い繁っていて出来なかった」と書いています。7月1に測量日記には、「午前6時過ぎに地震があった」と書いています。
【本馬(ほんま)】
江戸時代、幕府公用者や諸大名が一定の賃銭で使用できる宿駅の駄馬。その積荷量は軽尻(からじり:江戸時代、宿駅で旅人を乗せるのに使われた駄馬)の倍で、約四〇貫目であった。ほんうま。
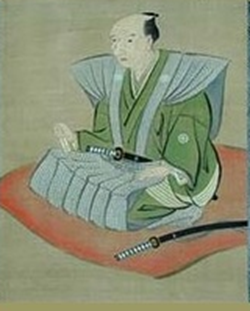
伊能忠敬像(伊能忠敬記念館蔵)

<忠敬が使用した測量器>
具測食定分儀(そくしょくていぶんぎ):日食・月食の欠ける様子を観測するために用いられました。

<忠敬が使用した測量器>
半円方位盤(はんえんほういばん):遠くの山や島への方位を測るための方位磁石盤。
2.鷹狩りの家康に鮮魚を送った冨浦の岡本村:
徳川家康は鷹狩りを大変好んでいました。家康は、鷹狩りをしながら、役人の姿勢や農民の状況なども調べたので、百姓が役人の暴政を訴えたこともありました。
家康が鷹狩りで東金に来ていた時、岡本村(現:原岡)から鮮魚が送られていた記録が原岡区の古文書「家康公様上総国東金卸成卸膳之卸肴差上覚」にあります。
この古文書によると、慶長19年(1614)から寛永7年(1630)までの間、徳川家康や秀忠が7回行ったので、鮮魚は63回送ったそうです。
その頃の岡本浦の漁師は、かつての里見水軍だったので、勇敢で行動範囲が広く、漁法も他の浦より勝っていたため、東金まで鮮魚を送るように命じられたようです。
慶長19年正月7日には、3人の飛脚により、「大だい三枚。すすき一本。ぼら一本。黒だい一枚。ぶだい三枚。こち二本。〆六色・数十一。」が送られました。
3.鯛の産地だった富浦:
富浦は、かつて鯛の産地として不動の地位を占めていました。そのきっかけは、和泉国(大阪府)堺から池田弥三兵衛(ヤソベエ)という人が渡って来て、関西地方の組織的な漁法と漁具が伝えたからです。
慶長8年(1603)、江戸に幕府が開かれると、江戸の街が大消費地になると考えた弥三兵衛は、自給自足程度の漁業の地だった石小浦へやって来て、地元の漁民を雇い、長縄(延縄)を使い、鯛漁を始めました。石小浦の海岸には岩礁を加工して、周囲20mもある円形の生簀(弥三兵衛生簀)もつくりました。漁場は房州の沿岸ばかりでなく、三浦半島や真鶴にまで及びました。獲った鯛は生きたまま押送船(鮮魚を専用に運ぶ、帆と櫓を併用する快速船)で江戸へ輸送しました。弥三兵衛の指導を受けて、富浦の鯛の漁獲量は関東屈指となり、相場を左右するほどに成長しました。この石小浦が、房州鯛漁の発祥の地であるという説があります。
「弥三兵衛生簀」は、明治以降もしばらく宮中の儀式に使う鯛の生簀として使われていました。
「南房総市の昔話、その他」から

昔の「弥三兵衛生簀」図

