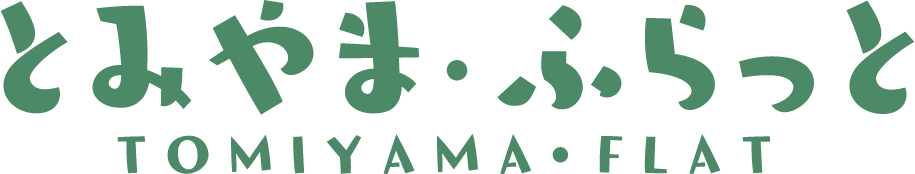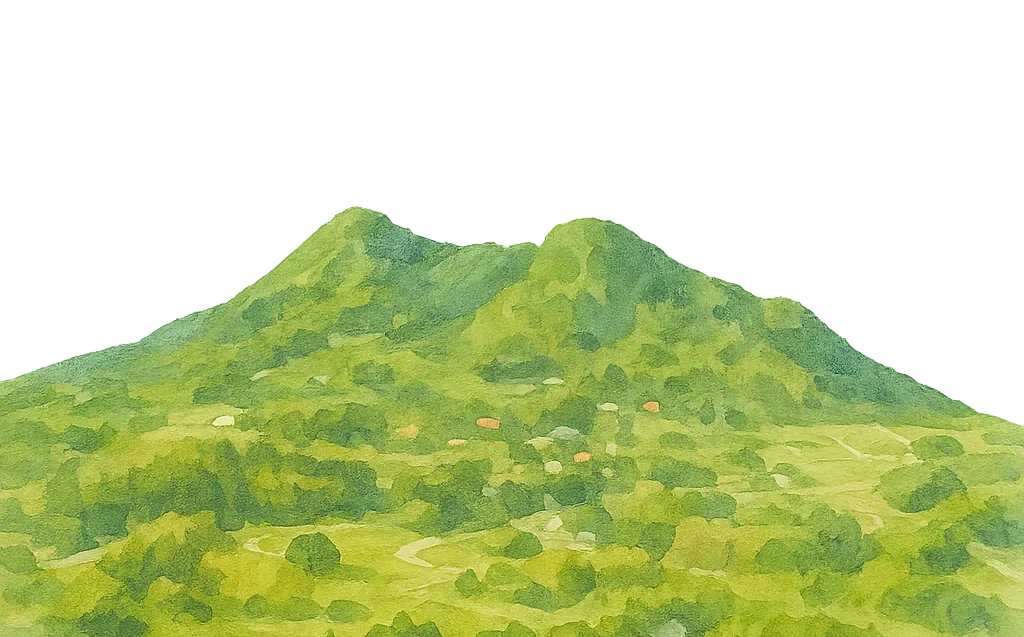今回のフットパスは、以下のコースを巡り、平群の風景を楽しみ、水野家のお花畑も訪れます。また、「乃木将軍の遺書報道」で名を上げた新聞記者:座間止水の生家を巡り、彼の功績について考えました。
●コース (約7.7km):
集合場所(旧松尾商店の隣の空き地)出発(9時)→座間止水生家・座間木材角経由→古道入口→正寿院下の道路→龍泉寺下経由→水野家南側の道路→水野家→水野家下の道経由→蛇喰集会所→大澤橋経由→集合場所(11時45分頃解散)
今回も多くの方々にご参加いただき有難うございます。_(_^_)_
晴れて暑い中、途中途中、川名修さんの史跡説明やクイズ、おやつを楽しみながら、皆様は元気にワイワイガヤガヤとウオーキングを楽しまれました。
最後のお土産(ネギや新玉ねぎ、胡瓜等の新鮮な野菜)を手に「次も楽しみにしていますよ!」と帰途に着かれました。
●今回の配布説明資料はウオーキング中の写真の後に記載されていますので、ご一読いただけると嬉しいです。😊

いつもの出発前の体操中!、ご参加者の車が多く、体操場所が狭かった!

出発前の明治天皇の崩御と野木将軍の殉死について説明中!

さあ、出発だ!

大特ダネ記事「乃木将軍の遺書」を掲載した国民新聞社の座間止水記者の生家があった場所の説明中!
-768x1024.jpg)
集落に入り口に飾られた大草鞋(辻切り)
の説明中!-1024x768.jpg)
大草鞋(辻切り)の説明中!

川上駅に向かう古道へ向かう途中での休憩&漢字クイズ中!

川上駅に向かう古道の説明中!
-1024x768.jpg)
ハナモモ園へ向かう途中の休憩中!(八雲の説明実施)

八雲神社

ハナモモ園へ向かう途中2!

ハナモモ園へ向かう途中3!
-1024x768.jpg)
ハナモモ園(残念ながらバラは咲いておらず、山百合は6月、残念!)

ハナモモ園の看板
-1024x768.jpg)
蛇喰地区へ向かう途中!(周りのバラ科の白い花々が綺麗!)
-768x1024.jpg)
バラ科の白い花(綺麗!)

蛇喰宮崎集会所前で蛇喰(じゃばみ)について説明中!

集合場所へ向かう途中1!
-1024x768.jpg)
集合場所へ向かう途中2!(休憩&漢字クイズ中!)
-768x1024.jpg)
お土産は新鮮野菜(ネギ、玉ねぎ、胡瓜)

お土産をお渡し中!
<配布説明資料>
平群を歩き、富山や伊予ヶ岳の風景をいろいろな角度から鑑賞します。
「ふらっとフットパス110(令和7年5月)」
1. 明治天皇の崩御と乃木将軍の殉死:
明治45年(1912)7月は、月初めから蒸し暑かったそうです。18日、明治天皇は、にわかに食欲が減退し、19日の夕刻から熱が出て、重体になったそうです。宮内省から明治天皇が重体だという発表があったのは、翌20日の午前10時30分で、午後には新聞の号外が出たそうです。
そして、30日の午前0時43分に心臓マヒをおこして崩御されたそうです。午前1時には、嘉仁皇太子の践祚(せんそ:天皇の位につく)の儀式が行われ、元号も「大正」と決定し、発表されたそうです。
明治天皇の葬儀(御大葬)は、9月13日に行われました。翌14日の朝、御大葬の記事を読もうと思って新聞を開いた人々は、そこに「乃木大将夫婦の自刃」という見出しを見て驚きました。
13日の午後8時に大葬開始の号砲が鳴りましたが、乃木夫妻はその直後に自殺したのです。遺書には、明治10年の西南戦争で軍旗を奪われ、死ぬ機会を待っていたが、天皇の死で覚悟を決めたと記されていたそうです。乃木稀典は、日露戦争の旅順総攻撃の失敗で、6万人の兵士を死傷させたことも負担になっていました。
2.大特ダネ記事「乃木将軍の遺書」:
昭和の評論家:大宅壮一は、その著書「炎は流れる」の中で、「明治―大正新聞史を飾る大特ダネは、乃木将軍遺書発表で、その主役を演じたのは、赤坂署の本堂平四郎署長と国民新聞社の座間止水記者である。」と記しています。
明治15年、平久里下に生まれた座間止水は、上京し、東京府師範学校に学び、明治43年には、徳富蘇峰が主宰する国民新聞の記者になりました。
乃木将軍の死の真相を知らせまいとする軍首脳に対し、世論を背負った新聞社は、遺書を手に入れようと腕利きの記者を動員しました。
座間止水は、遺書の実物は軍の大御所の山県有朋らの手に渡っているが、その写しが、検視した赤坂署にあるかもしれないと考え、旧知の間柄にあった本堂署長を訪ねました。交渉し、もう一押しだと考えた座間は、本堂の正義感に強く訴えるとともに、遺書の発表による責任は自分が取ると訴えました。
座間は、ふるえる手で遺書の全文を写し取り、赤坂署を出ました。「号外!号外!乃木将軍の遺書全文掲載」という声があがったのは、その後間もなくのことでした。座間止水は、その後、東京毎日新聞(毎日新聞の前身)の編集局長や読売新聞の社会部長になりました。

座間止水

本堂署長
3.古代の官道と駅:
養老2年(718)、安房国が設置されると安房国の国府(三芳の府中)へ至る道路が建設されたと思われます。延喜式によれば、安房国には、白浜駅と川上駅があり、駅馬(はゆま)が5頭常備されていたと言われます。
白浜駅は、最近の研究では国府に隣接するところ(現在の館山市正木辺りが白浜郷と言われた)に、国府湊を兼ねてあったと考えられています。
川上駅は、研究者の多くが富山地区の川上を想定しています。川上は、外房と内房をつなぐ東西の道と安房と上総をつなぐ南北の道の十字路に位置し、交通の要衝でした。安房路は、ここから丘陸を超え天羽駅(あまはのえき:上総湊近辺?)へ北上していました。
4.白蛇伝説が伝わる蛇喰(じゃばみ)地区:
蛇腹地区の小高い山の頂に、昔、城があったと言われています。この城は戦国大名の里見に関係があると思われますが、大変美しいお姫様がいたそうです。この姫様の噂は、近くだけではなく遠く上総の方にまで伝わり、美しい姫を奪おうとする者もいたそうです。
ある秋祭りの日、お姫様は氏神様にお参りをしましたが、その帰り道に一匹の白蛇が殺されているのを見つけました。お姫様は、白蛇を哀れに思われ、家臣に命じて蛇塚を建てさせ、お坊さんを呼んでねんごろに供養をしました。このようなお姫様の慈悲深い気持ちが通じたのか、この地区のさまざまな蛇がお姫様を慕って集まり、お姫様の健康を守ったと伝えられています。
蛇信仰には、実用的な理由も考えられます。蛇は、野ネズミの天敵で、「稲の守護神、田の神・倉の神・穀物神」等の神格が蛇に付加されています。
5.富山:
富山は、南北二峰から成る双耳峰の山です。北峰には金比羅宮があり、南峰には観音堂があります。北峰が高く、海抜349.5mです。房州の海が見え、遠く11か国(武蔵や相模など)が見え、遠見山とも呼ばれます。
忌部広成(いんべひろなり)という人が、大同2年(807)に書いた「口語拾遺」に、「天富命(あめのとみのみこと)が、阿波の斎部(いんべ)一族を引き連れ、房総半島へやって来た」と書かれています。天富命は房総の地を開拓するため、この山頂から指揮をとったとの説があり、また天富命が埋葬された地であるという説もあります。そのようなことから、この山の名前が、「富山(とみさん or とみのやま)」になったとされています。
天富命が上陸したとされる場所は、富崎(館山市)という地名になっていて、勝浦市には遠見岬(「とみさき」が変化したという説)神社があります。
南峰の観音堂の境内には、「ふじの山」の作詞で有名な巌谷小波(いわやさざなみ)の歌碑があります。歌碑には、
「山高きがゆゑに貴からず 曲亭翁の霊筆によりて この山の名長へに高く尊し 水茎(みずぐき:筆、筆跡)の香に 山も笑いけり」とあります。
「山高きがゆゑに貴からず」の部分について、ことわざ慣用句辞典によると、平安時代後期に起源をもつ子ども向けの教訓書である「実語教」という書物に載っていて、意味は、「山は高いということだけで価値があるのではなく、樹木が生い茂っているところに価値がある。何事も見かけにだまされないで、実質を見きわめよとの教え」と書いてあります。この部分は、NHKの番組「にっぽん百低山」のオープニングのナレーションで使われています。
6.伊予ヶ岳:
伊予ヶ岳は、古くから神々が降臨した山と考えられています。伊予ヶ岳のどこに祀られているかは不明ですが、少彦名命(すくなひこのみこと:大国主命の国づくりを補佐した神様)も祀られていると伝わります。弥生時代の頃、大陸から丹朱(水銀)や金を求めて日本列島に渡ってきた人々がいます。この中で採鉱や治金を司った一族が少彦名命を信奉していました。この一族は、紀伊、伊豆、安房、常陸へと渡ってきています。安房には朱や金にまつわる丹生や金束などの地名があり、その中心的位置にあった伊予ヶ岳に少彦名命が祀られ、少彦名命の終焉の地である伊予国大州の「伊予」の名前が山の名前として付けられたと、「東アジア古代文化を考える会」の榎本出雲氏は述べているそうです。
また、伊予ヶ岳は、「伊予国(愛媛県)の石鎚山」の別名の「伊予の大岳」に似ていることから「伊予ヶ岳」という名前になったという説もあります。石鎚山の「天狗岳」は、古い歴史を持つ「修験の霊場」であり、法起坊という天狗が住むと言われています。伊予ヶ岳の山頂の岩峰も修験の霊場にふさわしく、多くの修験者たちがここで修行したと考えられ、天狗伝説も伝わります。麓の天神社の別当寺だった神照寺には、修験僧が住んでいたと言われます。
明治5年の「修験道廃止令」により、神照寺は廃寺となりました。現在は、近くの泉龍寺が神照寺の観音堂等を管理しています。

石鎚山(いしづちやま):天狗岳(てんぐだけ)と呼ばれる峻険な山頂
<参考>
・ふるさと富山、他