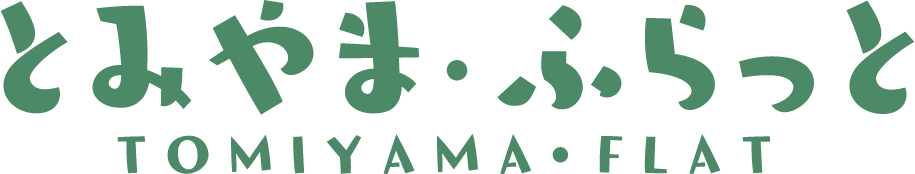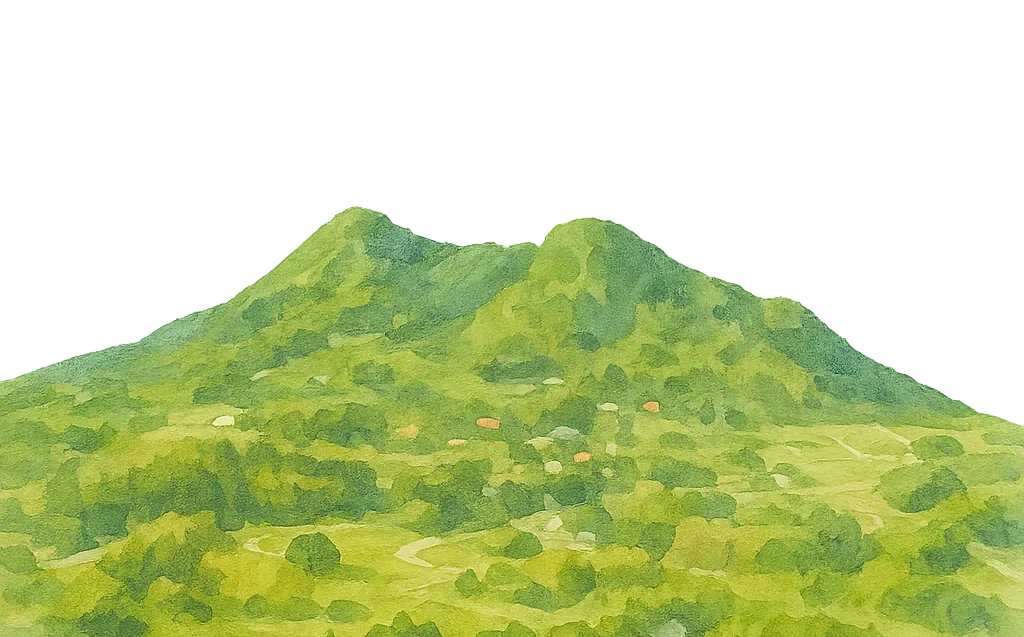富山町史』によれば旧山田村には江戸時代の初期に九十八件の小字がありました。
しかし現在残っている小字は三十六件です。なぜ小字は消えたのでしょうか。
実は消えた小字の一部は検地帳にある地主名の肩書きとして残っていたのです。
たとえば「もちの木八左衛門」「柿内太郎兵衛」というようにです。もうおわかりの方もいると思いますが、肩書きとも言える「もちの木」「柿内」は屋号です。
つまり小字は屋号として残っていることが多いのです。
これは資料の多く残っている平久里中や平久里下でも当てはまります。
ではなぜ旧山田村にはこんなに小字が多かったのでしょうか。
それは嶺岡や鴨川に抜ける街道沿いにあり一部の地区は江戸幕府の直轄領だったからだと思われます。
街道筋で様々な人の往来があり、住んでいた人も多かったはずです。
先に紹介した検地帳の小字の中には、職業屋号と思われる「鍛冶屋」「布めん」や地位のある者が住んでいた「とう屋敷」「古屋敷」という呼び名が記録されています。
「屋敷」とつけられた名は名主あるいは代官が住んでいたことでしょう。
現在も残る「御屋敷」という小字は街道沿いにある地名で、名主の川名四郎右衛門の住まいだったと記録されていました。
山田村では、名主は嶺岡牧を取り仕切る牧士もくしも兼ねる要職だったのです。
令和二年の山田地区の人口は一七三人ですが、江戸時代の山田村はにぎやかに人々が往来したことでしょう。
(徳永忠雄)